山門
本来の六所神社の山門は、霊仙寺の山門となっていると芳本清一郎先生にうかがった。
現霊仙寺の山門をここに当てはめて想像してみたが、少し派手すぎる様にも思える。
今は、静かな六所神社にふさわしい山門が建てられている。鳥居越しに、鳥居の中央から見る山門のバランスは丁度良いと感じる。
右の画像は、現霊仙寺の山門→
|
|
 |
|
ご神木・六本杉
足利尊氏が再起を祈念して手植えしか六本杉がご神木となっていたが、古木となり、樹勢が弱り樹医の診断を受けたが勢いは戻らず、伐採売却された。売却先は、佐伯市の平尾銘木店。
平成元年に最後の一本が切られた。売却金額は、最初のものが高価で3千数百万円、六本総額で1億円との事。
最後の杉の根元が輪切り状態で社務所に保管されている。また、海岸近くの「割烹梅乃屋」に六本杉の枝と云われるものが飾られている。
建武三年(1336年)官軍に敗れた足利尊氏が、国東の富来城主富来店蔵を頼って再起をはかったおりに参拝して祈願し、お手植えしたと伝えられている。
鬱蒼と茂る神木の姿を知りたいが・・・
「国東半島の歴史と民族 著者梅原治夫氏 昭和49年発行」 より拝借 → |
|
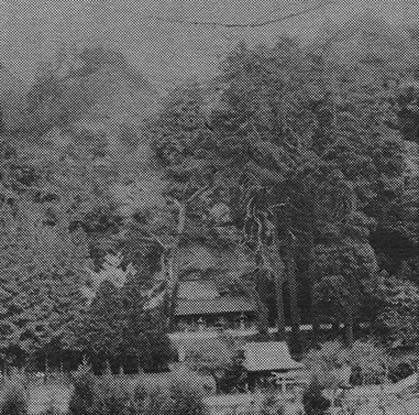 |
|
|
|
 |
|
境内左脇の社務所と思しき建物をのぞくと、写真の様な衝立が置かれ、説明書きが立てられている。説明書きには衝立と応接台と書かれているが、衝立しか見えない。
以下、説明書き転記
〈衝立・応接台〉 平成五年三月吉日
足利尊氏が戦勝祈願に植えたと言い伝えられた御神木六本杉が寄る年波には勝てず枯死寸前、昭和五十八年佐伯市平尾銘木店(社長平尾豊一郞氏)によって伐採、その根元を素材に大分高等技術専門校専門指導員(綿貫勝敏氏、野中巌氏)の卓越した技術の指導のもとに、生徒の協力を得て優秀な三日月形の衝立と応接台が完成した。六所神社の宝として永く保存されることになった。 |
|
 |
|
磨崖仁聞菩薩像
山門をくぐった右手に岩を彫った龕(ずし・ガン)に磨崖の仏像が彫られている。
中央が国東六郷満山の開祖である仁開菩薩、左は比丘尼(ビクニ:仏教において、出家して、定められた戒を受けて正式な僧となった女子のこと)、右は従者の比丘(ビク:出家して具足戒を受けた男子)像と云われているが、さだかで無い。
中央の像は、持ち物からの推測では役行者とも言われる?
この地区特有の角閃安山岩のに彫った仏は風化が激しく、その表情もいつまで見られるか心配である。
製作は、鎌倉末期から室町初期と推測されている。 |
|
今夷社
夷岩屋と呼ばれた窟に嵌り込む様に岩屋がつくられている。霊仙寺に置かれている小さな一対の狛犬はこの窟にあったものと云われる。
説明書き転記
| 今夷社(いまえびすしゃ) |
| 別 名 |
夷社(えびすさま) |
| 御祭神 |
時代主命(ことしろぬしのみこと)
大国主神の子・生産商業の守護神 あらゆることに通じ言魂(ことだま)の神と称えられる |
| 建 築 |
入母屋造軒唐破風 十九世紀初頭 |
| 祭 事 |
四月十四日 十二月十四日例祭 |
|
|
 |
|
大綿積社
説明書き転記
| 大綿積社(おおわたつみしゃ) |
| 別 名 |
龍神社(りゅうじんさま) |
| 御祭神 |
綿津見神(わたつみのかみ)
海神・海童・少童・少童海神とも称され海の神霊として広く信仰されている |
| 建 築 |
向唐造 柿葺 江戸時代後期 |
| 祭 事 |
四月十四日例祭 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
薬師堂 六所神社磨崖像
権現社の右手斜面をよじ登って行くと、窟に嵌り込む様に、朽ち果てる寸前の観音堂がある。中をのぞくと、無惨な姿の木仏が数体みられる。
その窟の左角に声聞形(せいもんぎょう)の座像磨崖仏が彫られている。
声聞形とは僧の形を意味している。僧形の意味は、八幡さまが仏の道にはいって権化(ごんげ:本地垂迹:ほんじすいじやく)したこと。仏説を聞いて道を悟った姿
を声聞形といっている。この姿を聖(ひじり)または尊者(そんじや)とよんでいる。
仏教の世界にあっては、古くは、釈迦の音声を聞いた弟子をいっているが、大乗仏教では縁覚(えんがく:他の教えによらず自ら覚る者)と菩薩に対する時は、釈迦の直弟子によらず教法によって三生六十劫(さんじょうろくじょうこう)の間四諦(したい:苦・集・滅・道)の理を観じ、自ら阿羅漢となるを理想とする一番低い仏道修行をなす者をいっている。その姿が声聞形である。
「国東半島の歴史と民族 著者梅原治夫氏 昭和49年発行」より |
|
 |